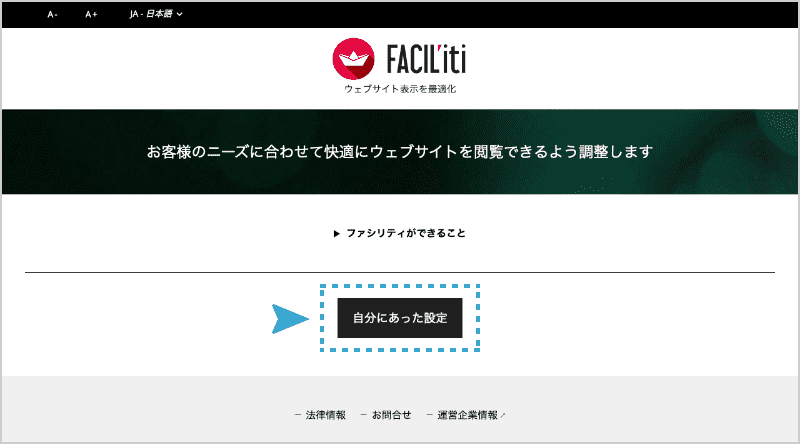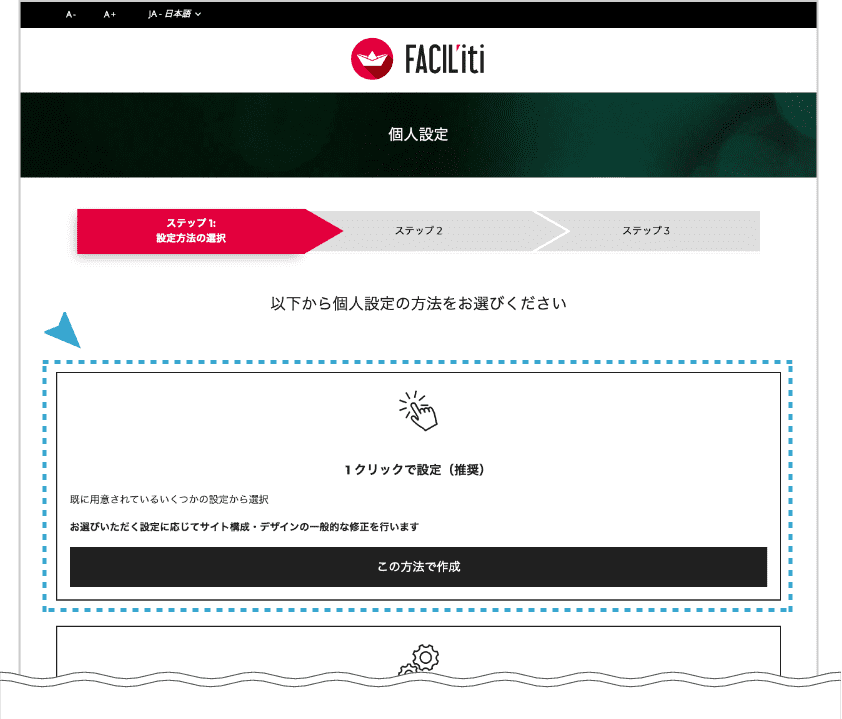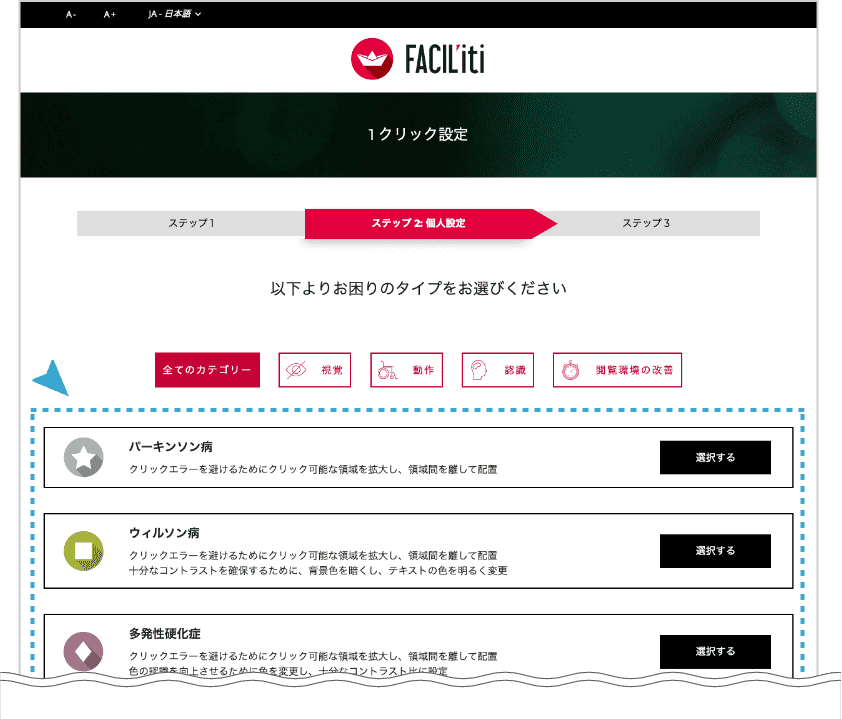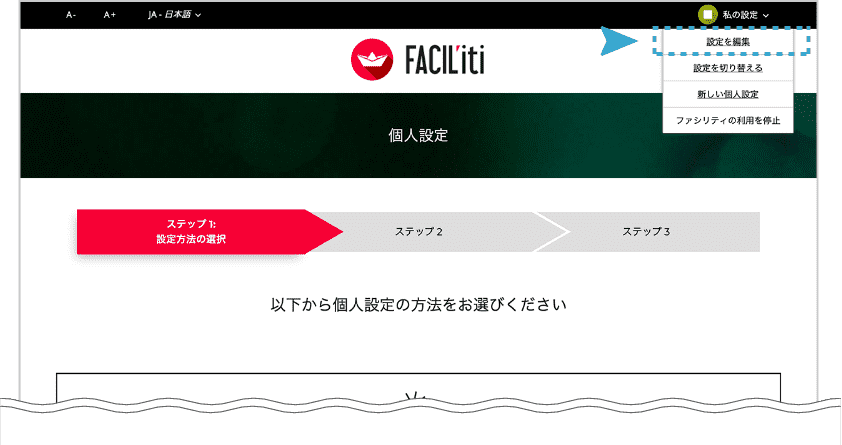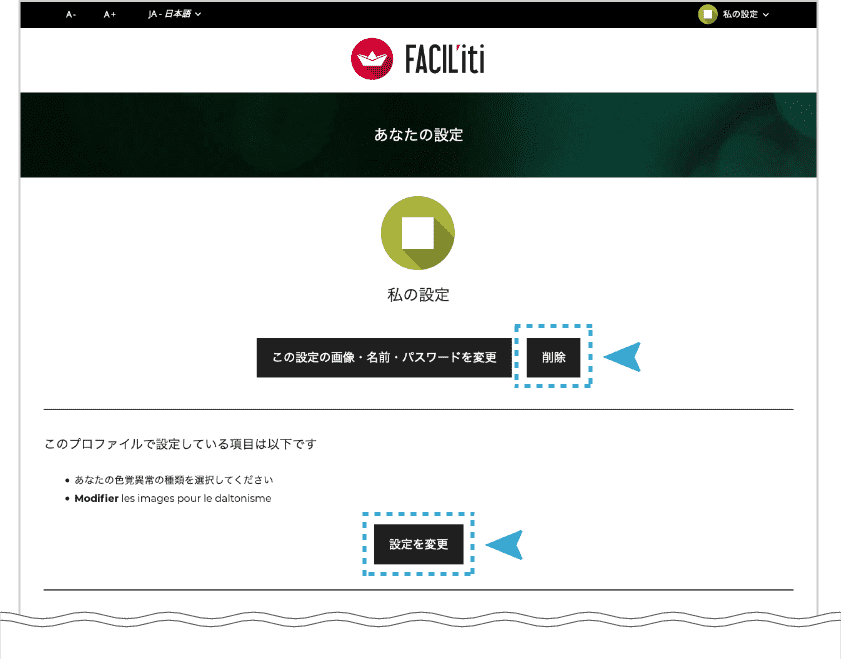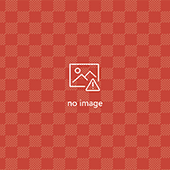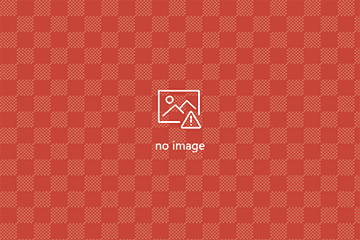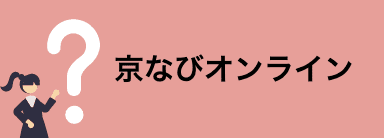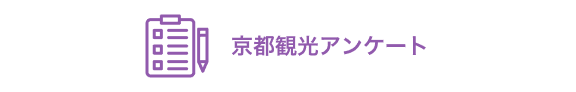新京極
北は三条通から南は四条通に至る約500メートルのこの通りを新京極通といい、通り名は平安京の最も東に位置した東京極大路(現在の寺町通)の東側に新しく作られた通りであることに由来する。 天正年間(1573~1592)、豊臣秀吉が市中の多くの寺院を寺町通に集めたことに伴い、その境内が縁日の舞台として利用され、周辺は見世物や催し物を中心に発展するようになった。 明治5年(1872)、このことに注目した京都府参事槇村正直は、東京遷都で衰えていた市民の士気を盛り上げるべく、寺院の境内を整理して、そこに新たな通りを造った。新京極通の誕生である。 明治10年(1877)頃には紙芝居、浄瑠璃、寄席などの興業場や飲食店などの多くの店舗が立ち並び、明治30年代には東京の浅草、大阪の千日前とともに、日本の三大盛り場として知られるようになった。 現在も、修学旅行生をはじめとする多くの観光客や買物客でにぎわう、京都を代表する繁華街である。 上方落語の始祖・安楽庵策伝が住職を務めた誓願寺、和泉式部の寺として知られる誠心院や、西光寺、蛸薬師堂妙心寺、安養寺、善長寺、錦天満宮、染殿院という由緒ある7つの寺院と1つの神社が通りの歴史を今に伝えている。 京都市
基本情報
| 正式名称 | 新京極 |
|---|---|
| よみがな | しんきょうごく |
この情報を共有する
-

Xでシェア
-

Facebookでシェア
-

LINEで送る

URLをコピー