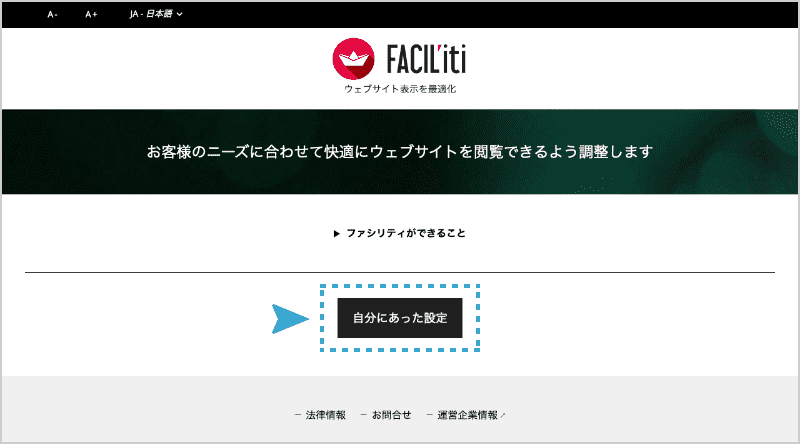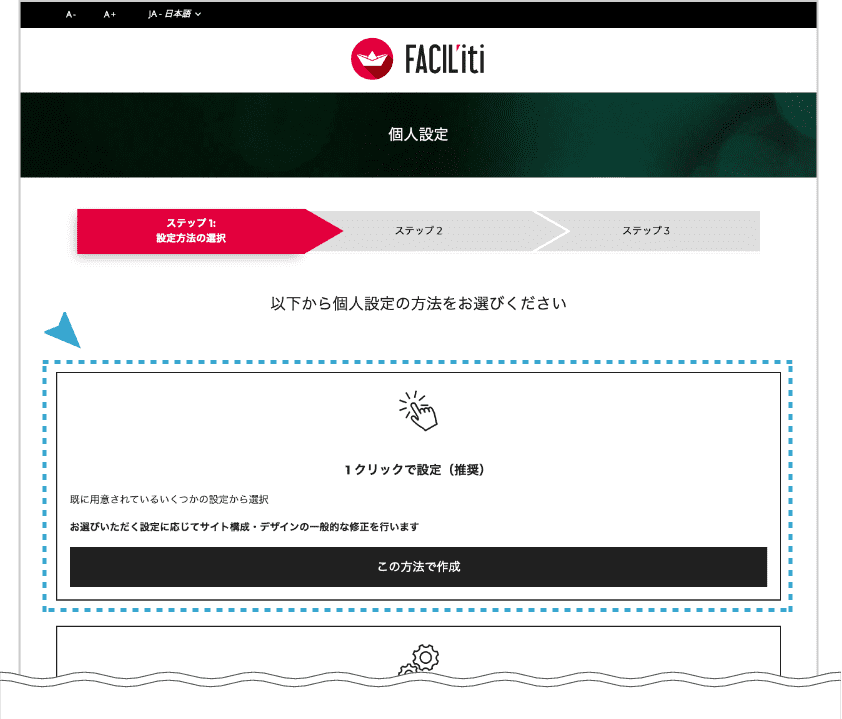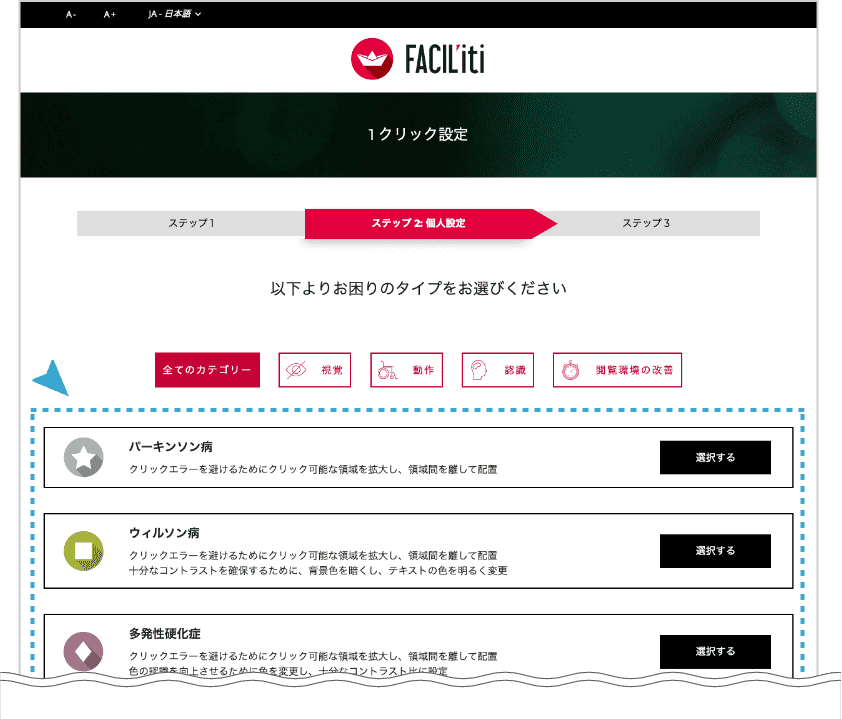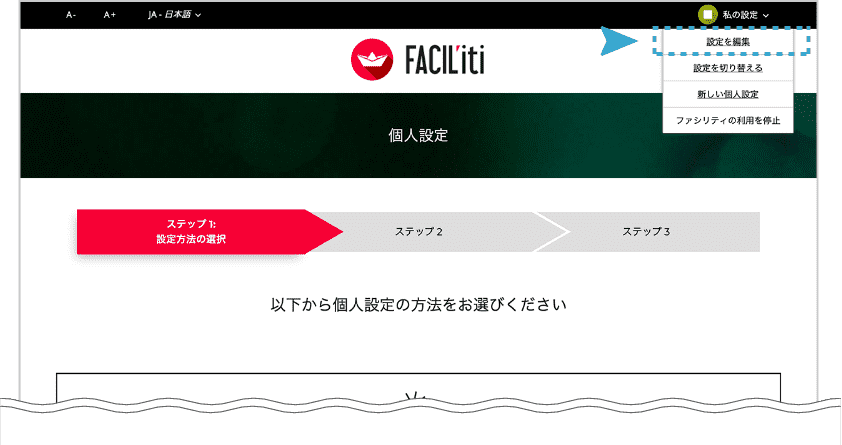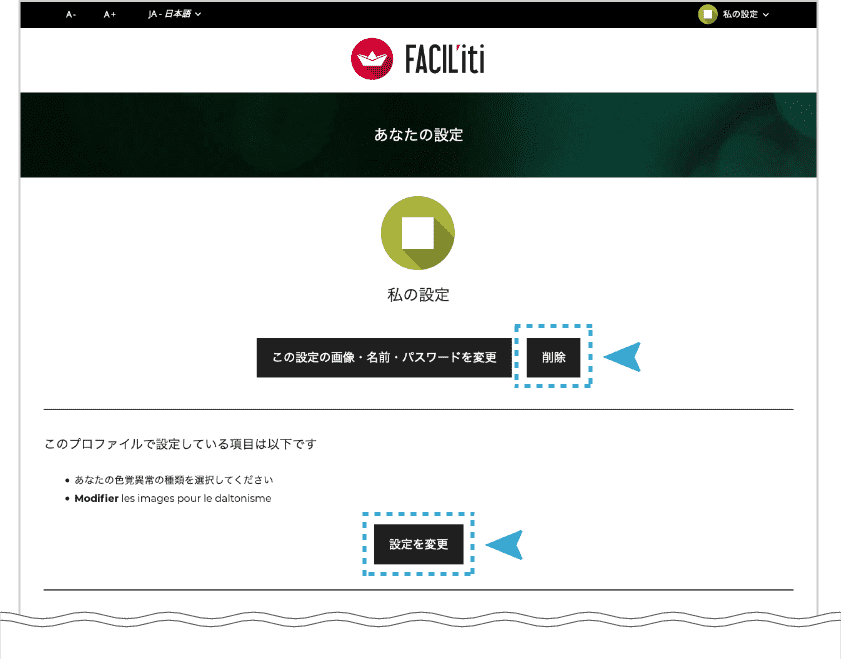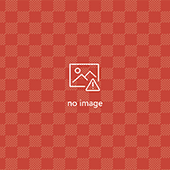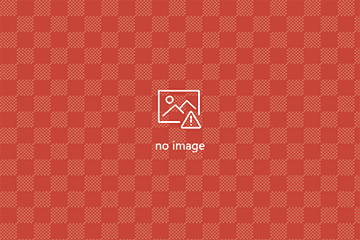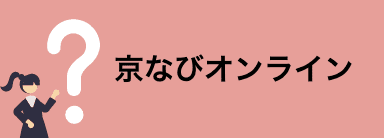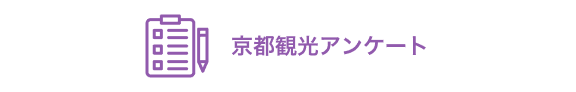八瀬天満宮社
祭神として菅原道真(すがわらのみちざね)(845~903)を祀る。
裏山中腹には、足利尊氏(あしかがたかうじ)に追われ比叡山へ逃れた後醍醐(ごだいご)天皇の行在所(あんざいしょ)(天皇が外出した時の仮の御所)があった「御所谷」、境内には、「後醍醐天皇御旧跡」、「復租紀恩碑」、「皇后陛下御歌碑」、「弁慶背比べ石」、「菅公腰掛け石」等の史蹟がある。 天満宮社の例祭は5月5日。
天満宮社には9つの摂社が祀られ、本殿南側の秋元(あきもと)神社は、宝永(ほうえい)7年(1710)比叡山との境界論争勃発の際、八瀬村の利権(租税の免除)を認めた裁決の報恩として、時の幕府老中で,この訴訟の担当者であった秋元但馬守喬知(あきもとたじまのかみたかとも)を祀り、以来毎年「赦免(しゃめん)地踊(ちおど)り」が奉納されている。
秋元神社の例祭「赦免地踊り」(八瀬郷土文化保存会執行)は10月体育の日の前日夜に実施される。
天満宮の鳥居の傍にあったが、現在本殿石段下の傍に移設している。以下記載されている通りである。弁慶がいたずらに比叡山より下げて来たものであるといわれている。石の高さは六尺有余と有るが、現在は約1m50cmぐらいである。33cmぐらいは土中に埋まっている。
■菅公腰掛石
菅原道真公が勉学の為比叡山に登る途中八瀬天満宮の隅で休息した石で、管公が没した後その師の法性房尊意阿闍梨が勧請以来、「管公腰掛石」として喧伝された由来が「山跡名志(正徳元年(1711)刊に記されている。場所は天満宮社より向かって左三社の左側の上に有。
■秋元神社
八瀬天満宮の境内にある神社。元禄年間(1688-1704)幕府の老中であった秋元但馬守喬知を祭る。喬知は当時比叡山と八瀬との境界争いを村民側に立って解決。この報恩のため没後村民が喬知の霊を祭ったのが起こり。毎年10月体育の日(祝日)の前日喬知を偲ぶ赦免地踊がある(10:00より約1時間ぐらい)。この日は燈篭祭りとして秋元神社前にて朝10:00よりお湯式を始めます。夜は20:00より赦免地踊りがあります。
基本情報
| 正式名称 | 八瀬天満宮社 |
|---|---|
| よみがな | やせてんまんぐうしゃ |
| 通称名称 | - |
| よみがな | - |
| 住所・所在地 | 左京区八瀬秋元町639 |
| アクセス | ○京都バス17 京都駅前からふるさと前 徒歩約1分 ○京都バス19 国際会館駅前からふるさと前 徒歩約1分 |
| 開催日時 | - |
| 営業時間 | - |
| 定休日 | - |
| TEL | - |
| ホームページ | - |
この情報を共有する
-

Xでシェア
-

Facebookでシェア
-

LINEで送る

URLをコピー