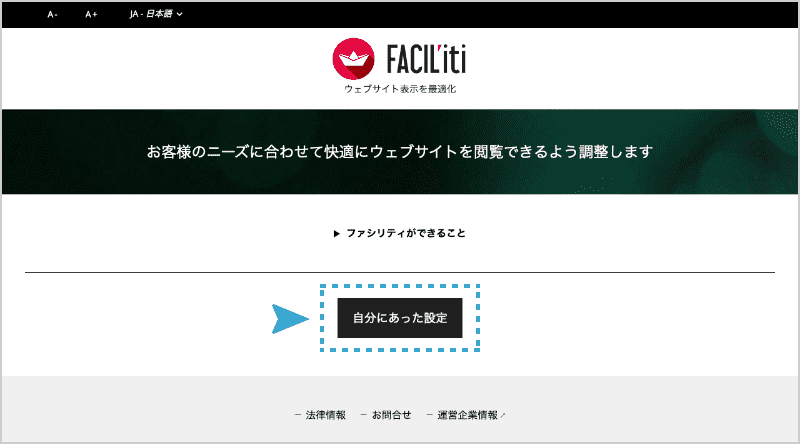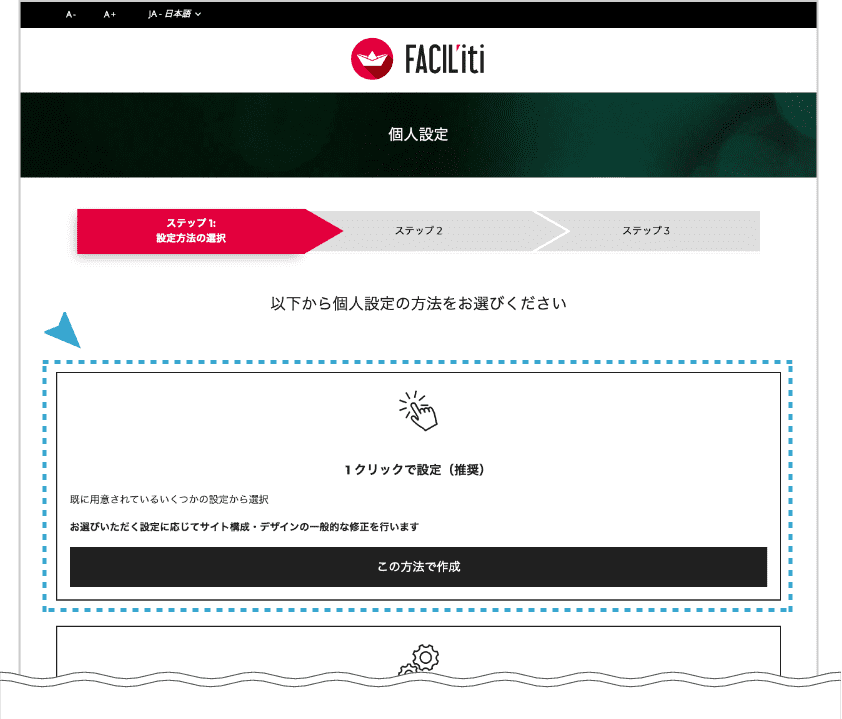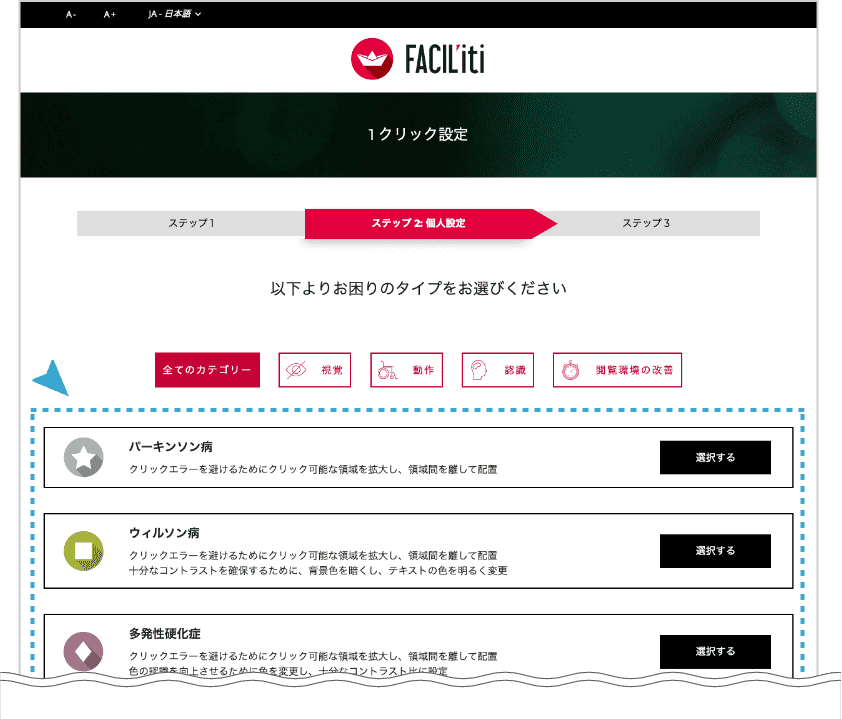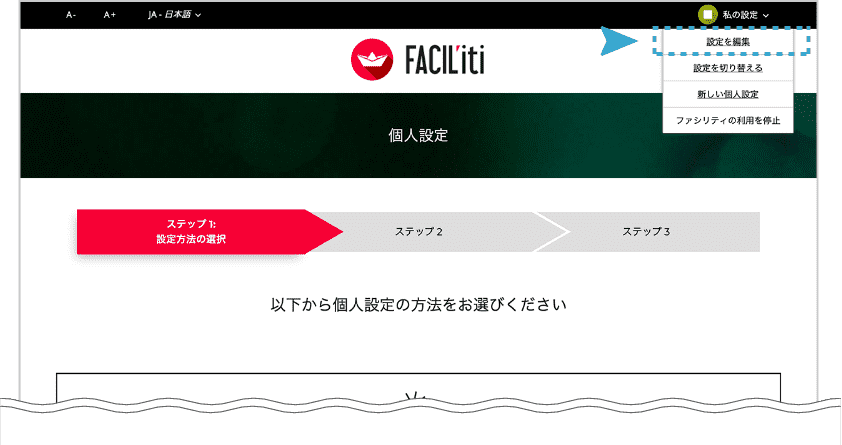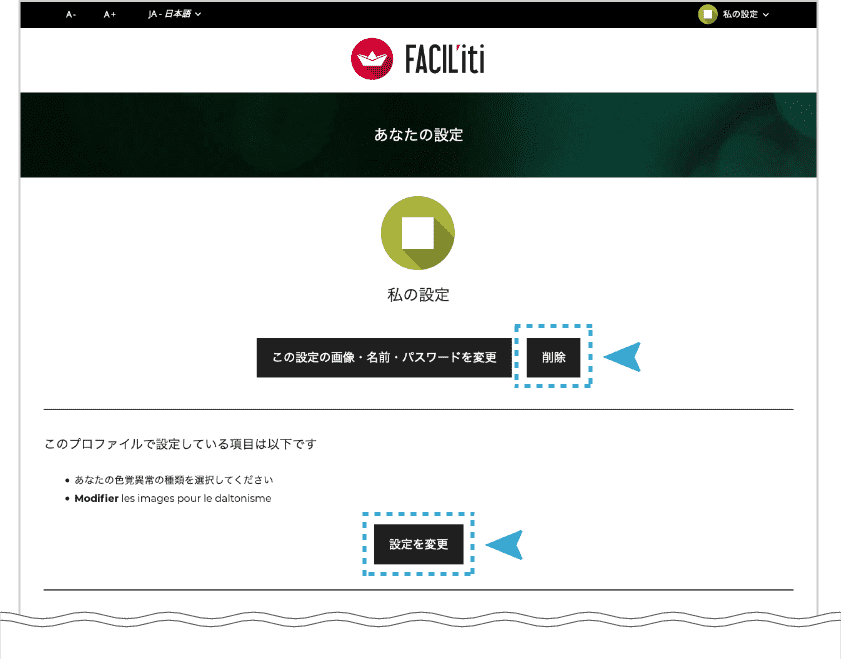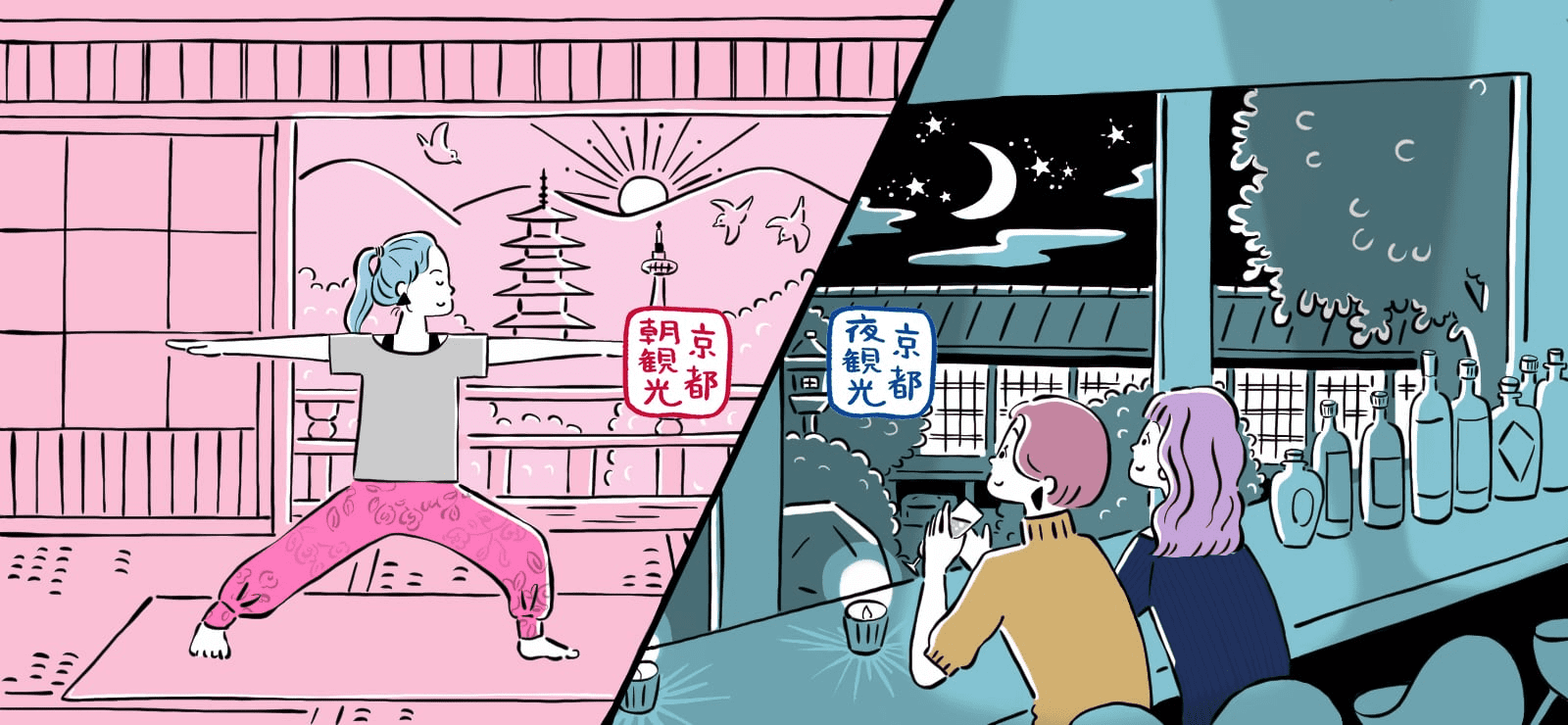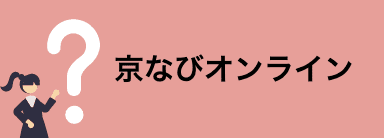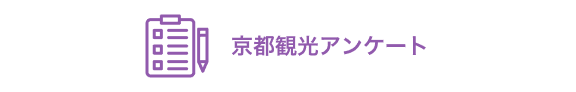2025年03月31日(月)
大正6年創業 西陣の老舗銭湯へ〜長者湯〜
大事に受け継がれて100年以上
美術館やギャラリーとはひと味違った体験ができる「アート」なスポットをご紹介。今回は、アートな銭湯の第1回目、老舗銭湯の「長者湯」です。昔ながらの銭湯に残る美しさをたずねます。最後の特典もぜひチェックしてください。

京都を旅した後は、日本のアートが感じられる銭湯で汗を流して気持ちよく。ということで、やってきたのは上京区にある「長者湯」。こちらは大正6年に創業した、地元のご年配の方から若い方まで愛されている銭湯です。

ご案内いただいたのは、3代目の間嶋正明さん。スキーが趣味で、冬になるとご夫婦で信州まで行き、日帰りで滑ってくるという60代の年齢を感じさせないパワフルさとおちゃめな面を持つお方です。
「うちは小さな銭湯ですけど、昭和初期の佇まいだから観光の人も来てくれはるんです」との言葉通り、外観も内観も基本的には昭和11年に全面建て替えした時のまま。昔、中国では神聖なところに設けられたという唐破風の屋根も風格たっぷり。日本では清潔になるところの証として銭湯でも取り入れられたといい、伝統的な銭湯建築を受け継いでいることがよくわかります。もちろん中に入っても、長い時間をかけて大事に使われてきたものでいっぱいでした。
 昔ながらの鶴亀錠の木製下駄箱
昔ながらの鶴亀錠の木製下駄箱
すべてはお風呂に入って気持ちよくなってもらうため

高い格天井に柳行李の並ぶ棚、壁も窓枠も梁、浴室入口の屋根部分まで、木の温もりにあふれた脱衣場。籐の床はぴかぴかで歩き心地もよし。聞けば営業前の11時くらいから床をふき、浴場も掃除して、夜12時に営業が終わったら再び浴場を掃除し、脱衣場にも掃除機をかけて、汚れなどが残らないようにしているとか。「おやじとおふくろからよう言われたんです。うちはね、掃除やと。そやからどこの銭湯にも負けへんキレイさがある。おふくろなんかは、ほんまずーっと下向いて掃除をしてたね」と語る間嶋さん。代々、大事にしているおもてなしの心を感じます。

親と一緒に来た子どもは、庭の鯉の数を数えて遊ぶそうです
初代の遊び心もふんだんに散りばめられており、珍しいものがいろいろ。脱衣場の一角にある休憩スペースの外を見ると、「あれは雪見灯籠いうて、先々代が嵐山から牛車に乗せて運んできたって聞いてます。同じものが円山公園の池にあってね。あちらは遠いから小さく見えるけど、うちはすぐそばなんで大きいでしょ」。下の窓を開けると、池があるから涼しい風が入ってくるとか。小さな庭は夏に良い役目を果たしています。

 浴室の入口を飾るのは、立派なタイル絵。男湯側は雪景色の金閣寺で、女湯側は春の清水寺です。華やかなアートがいいですね。「釉薬をかけて焼いたタイルでできてるんです。そやからペンキで描いたタイル絵と違って、何年経っても古くならへんのです」と間嶋さん。
浴室の入口を飾るのは、立派なタイル絵。男湯側は雪景色の金閣寺で、女湯側は春の清水寺です。華やかなアートがいいですね。「釉薬をかけて焼いたタイルでできてるんです。そやからペンキで描いたタイル絵と違って、何年経っても古くならへんのです」と間嶋さん。
 男湯と女湯の仕切り壁の上には、これまたアートな細工物が。先代が加賀で買ってきたという近江八景の透かし彫りが入った欄間。主人が代わるごとに、ちょっとずつ豪勢にされたんですね。余談ですが、こちらの銭湯は2007年公開の映画『舞妓Haaaan!!!』の撮影が行われたところでもあり、絵になる銭湯なんです。
男湯と女湯の仕切り壁の上には、これまたアートな細工物が。先代が加賀で買ってきたという近江八景の透かし彫りが入った欄間。主人が代わるごとに、ちょっとずつ豪勢にされたんですね。余談ですが、こちらの銭湯は2007年公開の映画『舞妓Haaaan!!!』の撮影が行われたところでもあり、絵になる銭湯なんです。
 年季の入った柳行李だって銭湯の一部。見ると少し壊れているものがあるような・・・「使う前にお客さんがバーンバーンって中のほこりをはたくから、どうしてもいたむんです」。修理できる職人が兵庫県にしかいないため、なかなか修理に出せないのが悩みで、ボンドで補修してやりくりしているとか。「長者湯」に来たらやさしく使いましょう。
年季の入った柳行李だって銭湯の一部。見ると少し壊れているものがあるような・・・「使う前にお客さんがバーンバーンって中のほこりをはたくから、どうしてもいたむんです」。修理できる職人が兵庫県にしかいないため、なかなか修理に出せないのが悩みで、ボンドで補修してやりくりしているとか。「長者湯」に来たらやさしく使いましょう。

計量器で有名なイシダの体重計の第1号機なんてものも。貫匁で重さを計る年代物で、おそらく明治時代のものじゃないかとのこと。味がある「用の美」を感じます。もちろん今も現役。女湯に置かれているので、女性の方はぜひ乗ってみてください。
アートという観点で日本の美にいろいろ着目しましたが、すべてがお風呂に入って気持ちよくなってもらうためと間嶋さんは話します。「ええお湯やったよ、ありがとうって言ってもらえるのがうれしいんですわ」。
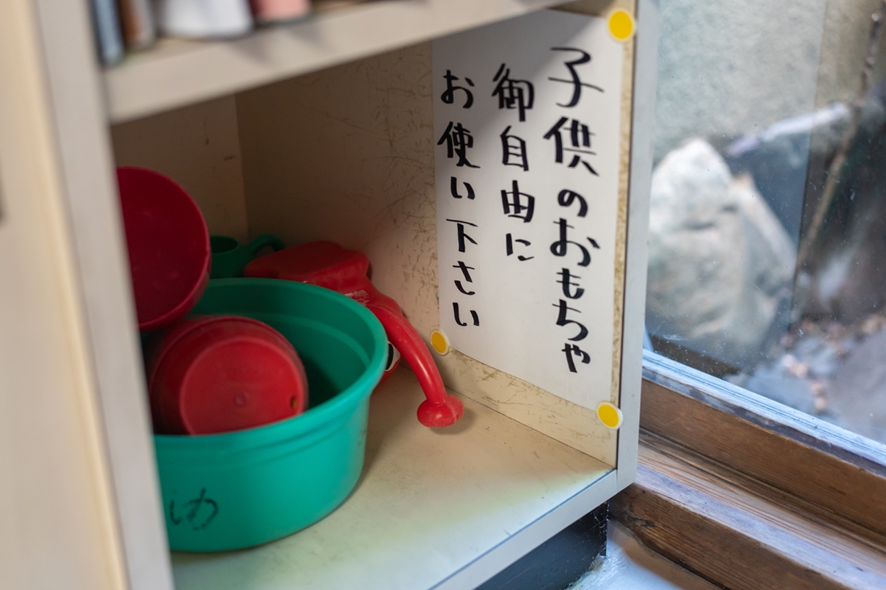
いい湯だな、地下水のお風呂

ではそろそろ肝心の浴場へ。洗い場と3種類のお風呂、サウナと水風呂があり、天井は高く開放的です。そしてキレイ。「カランとか新しくして、下のほうのタイルも替えたけど、上のほうとか風呂場のタイルはだいたい昔のまんまですわ」と、こちらも掃除を徹底されています。
あったかいお風呂は、肩までつかれる深風呂の「うたせ湯」と、ジェットの刺激が気持ちい浅風呂の「すわり風呂」。ぬるめの薬湯もあり、好みのお風呂に入れるのがうれしいです。「うちのお風呂のお湯は、地下水でくみ上げた水を薪で沸かして、ろ過して使っておってね。軟水のお湯やから、まったりしててやわらかいし。芯からあったまるよー」と間嶋さん。京都の地下水といえば有名で、豆腐屋さんなどたくさんの水を必要とする仕事では、昔から地下水が使われています。そんな地下水をお風呂でふんだんに使っているというのだから贅沢です。

そしてこちらが、間嶋さんがずっとほしかったというサウナ。「昔は京都市内に600軒以上あったのに、今(2025年)は79軒しか銭湯が残ってへんのです。昭和30年代まではお客さんも多くてよかったけど、どんどん銭湯に行く人が減ったからね。うちも、もうあかんって頃があって、おやじに『サウナいれよう』って言うたことがあったんです。でも『うちみたいに小さい銭湯にはいらん』って。そやからサウナを入れたんは、2023年10月のリニューアルの時やね。サウナを入れて、水風呂も拡張したら若い人も増えて、常連の方も喜んでくれて、ほんまよかったですわ」。ヒノキ張りのサウナ、気持ちいいですよ。

もちろんサウナの後に入る水風呂の水も、ろ過しただけの地下水。年中17~18度くらいと安定した水温なので、京都の地下水がじかに感じられます。
なお、薬湯では、毎月26日の風呂の日はほうじ茶の湯、冬至のゆず湯など時々変わった湯も楽しめます。間嶋さんの友人の農家の方が持ってくるよもぎを使ったよもぎ湯の日もあるそうで「よもぎの葉を洗濯ネットに入れて両手でしっかりもんで、お湯に入れるんですわ。天然の香りはやっぱり格別やね」。
薪で沸かしたお風呂はやっぱり違う
最後に店の裏でおもしろいものを見せていただきました。それが釜場と井戸。お風呂に入りに来た人であれば見せていただけます。
 薪で沸かしている銭湯は市内でも10軒くらいしかないとか。普段は見えない仕事にも、銭湯文化が垣間見えます
薪で沸かしている銭湯は市内でも10軒くらいしかないとか。普段は見えない仕事にも、銭湯文化が垣間見えます
 薪は工務店の方からもらう廃材などをチェーンソーでカットして用意。たくさん使うので、大変なお仕事です
薪は工務店の方からもらう廃材などをチェーンソーでカットして用意。たくさん使うので、大変なお仕事です


井戸ってどこだろうと思っていると、床下へ入っていくことに。ちょっととまどいながら間嶋さんについていくと、まさかこんな深い井戸が奥にあるとは驚き。「冬場は水位が下がるけど、梅雨の時期はすごい上までくるんよ」。
銭湯文化を守って、昔ながらの造形美を残す「長者湯」は、まさに日本アートの宝庫。いつも使う人がいて、京都の日常の中に溶け込んだアートです。伝統の担い手も間嶋さんから息子さんの4代目へと、すでに受け継がれているとのこと。これからも愛されること間違いなしですね。ぜひ「長者湯」で旅の疲れを癒してください。


インタビュー協力

間嶋 正明 さん
長者湯3代目
今回のスポットの基本情報
長者湯
【住所】京都市上京区上長者町通
【電話】075-441-1223
【アクセス】市バス「堀川下長者町」バス停から徒歩5分
※詳細情報は、公式Xよりご確認ください
ライター・カメラマン情報
ラーター【渡辺 良】、撮影【吉田 努】
今回の記事制作担当
株式会社グラフィック
20年間にわたり京都観光のフリーペーパー「京都いいとこマップ」を発行。現在は、京都いいとこウェブ(https://kyoto.graphic.co.jp/)、京都いいとこフォト(https://www.instagram.com/kyoto_iitoko/)、京都いいとこ動画(https://www.youtube.com/@KyotoiitokoVideo)を運営。